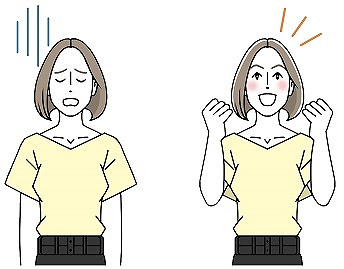双極性障害は、気分の波が極端に変動する精神障害の一種です。
主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
1.気分の極端な変動
双極性障害の最も特徴的な症状は、気分が極端に変動することです。
うつ状態と躁状態という2つの極端な気分が交互に現れます。
うつ状態では抑うつや無気力感、絶望感が強く現れます。
一方、躁状態では興奮や多弁、無謀な行動が見られることがあります。
2.エネルギーと活動量の変動
躁状態では活動量が増加し、エネルギーが高まります。
逆に、うつ状態ではエネルギーが低下し、日常生活に対する関心や動機が著しく減少します。
3.睡眠障害
双極性障害の人は睡眠障害を経験することがあります。
躁状態では睡眠が少なくても問題なく感じることがありますが、うつ状態では眠れないことがあります。
4.集中力の低下
気分が変動することにより、集中力や注意力が低下することがあります。
特に躁状態では多くのことに興味を持ち、一つのことに集中することが難しくなります。
5.自己肯定感の変動
気分の変動により、自己肯定感も変動します。
躁状態では自信過剰になることがあり、うつ状態では自己否定感が強まることがあります。
※これらは一般的な症状であり、個々の症例によって異なる場合があります。
双極性障害の診断と治療には、精神科医や心理医との専門的な相談が必要です。
双極性障害 原因
双極性障害の原因については、まだ完全に理解されているわけではありませんが、複数の要因が関与していると考えられています。
主な原因や関連要因には以下のものが挙げられます。
1.遺伝的要因
双極性障害は遺伝的な要因が関与していると考えられています。
家族歴に双極性障害を持つ人がいると、その個人が双極性障害を発症するリスクが高まる傾向があります。
2.神経化学的要因
脳内の神経伝達物質や神経回路の異常が双極性障害の原因とされています。
特にセロトニンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質のバランスの変化が関与していると考えられています。
3.ストレスや環境要因
長期間にわたるストレスや精神的な負担、生活環境の変化なども双極性障害の発症に関与する要因とされています。
特に感情の起伏が激しい状況やストレスが大きい状況で発症することがあるといわれています。
4.薬物の影響
薬物やアルコールの乱用が双極性障害の発症や症状の悪化に関与することがあります。
特に躁状態を増強する可能性がある薬物やアルコールは慎重に扱う必要があります。
※これらの要因が単独で発症を引き起こすのではなく、複合的に関与して双極性障害が発症すると考えられています。
ただし、個々の症例によって異なるため、正確な原因や発症メカニズムはまだ完全に解明されているわけではありません。
双極性障害 なりやすいタイプ
双極性障害には、特定の性格傾向が関連していると考えられています。
以下に、双極性障害になりやすいとされる性格傾向をいくつかご紹介します。
1.循環気質
社交的でほがらかで、他人との調和を大切にする性格です。
共感性や協調性を大切にし、他人への気配りも上手で周囲と同調していこうとする性格が特徴です。
2.発揚気質、刺激性気質
躁病の最軽症型としての発揚気質・混合状態の最軽症型としての刺激性気質が提唱されています。
発揚気質は、気分が常に高く前向きで、自信にあふれている性格です。
刺激性気質は、気難しく不機嫌で、イライラしているのが目立ちます。
3.執着性格、メランコリー親和型性格、マニー親和型性格
熱して冷めにくい執着性格、秩序を重んじるメランコリー親和型性格、自己を強く持っているマニー親和型性格が気分障害との関係が深いです。
これらの性格傾向を持つ人は、双極性障害に自然と発展していきやすい要素があります。
しかし、これらの性格傾向があるからといって必ずしも双極性障害になるわけではありません。
また、双極性障害は「双極Ⅰ型」と「双極Ⅱ型」の2つのタイプがあり、これらの違いは主に躁状態の程度によるものです。
※自分の性格傾向を理解し、悪循環に入る前に気づくことが大切です。
もし心配な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。
双極性障害 治療
双極性障害の治療には、薬物治療と心理社会的治療の2つの主要なアプローチがあります。
1.薬物治療
双極性障害では、躁状態やうつ状態を改善し、再発を防ぎ、症状を安定させるために薬物治療が重要です。
主に「気分安定薬」と「抗精神病薬」が用いられます。ただし、症状がおさまったからと言って、自己判断で薬を飲むことをやめてしまうと再発に繋がるケースが多いです。
2.心理社会的治療
心理社会的治療は、薬物治療と併用して回復に向かっていく治療法です。以下のような治療法があります。
・心理教育
病気を自らでコントロールできるようにするため、本人自身が病気を理解することが必要です。
・家族療法
家族の理解を強め、協力の体勢が治療には必要不可欠です。
・認知療法
小さなことからでも自分を褒め、肯定的に考えることが重要です。
・対人関係、社会リズム療法
人間関係のストレスを改善することで再発を防止できます。
<副作用>
薬物治療では、服薬による副作用が発生する可能性があります。以下のような症状が出た場合、一刻も早く専門医にご相談ください。
・気分安定薬
手足の震え、のどが渇く、下痢、尿量の減少など
・抗うつ薬
くちが渇く、便秘、眠気。胃腸障害、頭痛など
※双極性障害の治療は、自らが病気だと認識し、飲み続けることが重要です。
また、家族を含めて病気を理解し、生活リズムを大切にしながら、上手に付き合っていく必要があります。
双極性障害 ガイドライン
双極性障害の診断と治療に関するガイドラインは、国や地域によって異なりますが、一般的なガイドラインには以下のような内容が含まれています。
1.診断基準
双極性障害の診断基準は、通常、精神障害の診断基準であるDSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル)やICD-10(国際疾病分類第10版)に基づいて行われます。
これらの基準には、気分の変動、活動量の変動、睡眠障害、注意力の低下などの症状が含まれています。
2.病歴の評価
医師は患者の病歴を詳しく評価し、遺伝的要因や薬物使用、精神的ストレスなどの関連要因を把握します。
家族歴や過去の精神疾患の有無も重要な情報です。
3.薬物療法
双極性障害の治療には、気分安定剤や抗うつ剤、抗精神病薬などの薬物が使用されることがあります。
治療には個々の症状や病態に応じて適切な薬物を選択することが重要です。
4.精神療法
薬物療法と併用して、認知行動療法や対人関係療法などの精神療法が行われることもあります。
これにより、感情の管理やストレスへの対処能力を向上させることが目指されます。
5.定期的なフォローアップ
患者は定期的に医師とのフォローアップを受けることが推奨されます。
症状の経過や薬物の効果、副作用の評価、生活習慣の見直しなどが行われます。
6.生活指導
健康な生活習慣の維持やストレス管理、規則的な睡眠などの生活指導も重要です。
これにより、症状の悪化を防ぎ、治療効果を最大化することが期待されます。
※これらのガイドラインは専門家によって定期的に更新され、最新の診断と治療の知見に基づいています。
地域や医療機関によって異なる場合もあるため、具体的な治療計画は医師との相談に基づいて決定されることが重要です。