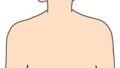小腸内細菌異常増殖症(SIBO: Small Intestinal Bacterial Overgrowth)は、通常大腸にいる細菌が小腸に異常に増殖した状態を指します。
主な症状は以下の通りです。
・腹部膨満感、腹痛
・下痢や便秘などの便通異常
・おなら、おくび-栄養障害(ビタミン欠乏など)-体重減少
SIBOでは小腸での細菌の異常増殖により、消化吸収障害が起きるためです。
そのため、栄養素の吸収不良による栄養失調を引き起こす可能性があります。
症状の重症度は個人差があり、軽症の場合は自覚症状に乏しいこともあります。
一方で、重症化すると体重減少や電解質バランスの異常など全身状態に影響を及ぼす恐れがあります。
小腸内細菌異常増殖症 原因
小腸内細菌異常増殖症(SIBO)の主な原因は以下のようなものが挙げられます。
1.消化管運動障害
小腸の蠕動運動が低下すると、細菌が小腸に停滞し増殖しやすくなります。
糖尿病や全身性強皮症など自律神経障害を伴う疾患や、手術後の瘢痕(はんこん)などが原因になることがあります。
2.解剖学的異常
空腸の盲ループ、腸重積、潰瘍性大腸炎による回腸嚢肛門吻合などにより、細菌が停滞しやすい環境ができます。
潰瘍性大腸炎の手術治療では、炎症の母地となる大腸を全て取り除きます。
そして小腸の断端を15cm程折り返して袋を作ります。
これを回腸嚢(かいちょうのう)といい、術後便を貯める機能を持たせ、この回腸嚢と肛門を吻合して肛門から排便できるようにします。
3.胃酸分泌の低下
胃酸が細菌を死滅させる働きを持っているため、胃酸分泌の低下は細菌の小腸への逆流を助長します。
胃切除術後や薬剤性の原因があります。
4.膵臓、胆嚢機能障害
膵液や胆汁は細菌増殖を抑制する働きがあるため、その分泌障害は細菌増殖を助長します。
5.免疫機能障害
免疫不全状態では、細菌に対する防御機構が低下するため細菌が増殖しやすくなります。
6.抗生物質の乱用
抗生物質の長期連用で腸内細菌叢のバランスが崩れ、異常増殖を助長する場合があります。
※このように、様々な要因が単独あるいは複合して、SIBO発症の原因となります。
正確な原因特定が重要で、内視鏡検査や画像検査、呼気ガス検査などが行われます。
小腸内細菌異常増殖症 治療
小腸内細菌異常増殖症(SIBO)の治療には以下のようなアプローチがあります。
1.抗生物質治療
SIBOの第一選択治療は抗生物質療法です。
主に以下の抗生物質が使用されます。
・リファキシミン
・メトロニダゾール
・アモキシシリン クラブラン酸
これらは腸管からほとんど吸収されない非吸収性の抗生物質で、小腸内の細菌を選択的に減らすことができます。
通常2~4週間の内服治療が行われます。
2.薬物治療
プロキネティック剤(intestinor、モサプリドなど)を併用し、小腸の蠕動運動を改善することで細菌の排出を促します。
3.食事療法
発酵性の高い食品(乳製品、小麦製品など)を控え、小腸での発酵を抑えることが重要です。
FODMAP食などの食事制限が試みられます。
FODMAP食とは FODMAPとは、小腸で吸収されにくく大腸で発酵しやすい糖質の総称です。
以下の頭文字を組み合わせた言葉です。
F: Fermentable(発酵性)
O: Oligosaccharides(オリゴ糖)
D: Disaccharides(二糖類)
M: Monosaccharides(単糖類)
A: And(および)
P: Polyols(ポリオール)
4.改善困難例への対応
SIBOが再発しやすい場合は、抗生物質のローテーション療法や、リファキシミンの継続投与が行われる場合があります。
リファキシミンは、キシファクサンなどの商品名で販売されている抗生物質であり、肝性脳症、過敏性腸症候群、旅行者下痢の治療に用いられます。
サルモネラを含むいくつかの種類の下痢には効果がありません。
経口投与される。
根本原因の治療が必要な場合もあります。
5.手術療法
解剖学的異常が原因の場合は、手術による異常部位の切除が行われることがあります。
※このように、抗生物質や食事制限などの保存的治療が中心ですが、原因に応じた対症療法が重要視されます。
治療に反応しにくい難治性のSIBOも多く、原因検索と根本治療が課題となっています。
小腸内細菌異常増殖症 予防
小腸内細菌異常増殖症(SIBO)の予防には以下のようなポイントがあります。
1.適切な食生活
発酵性の高い食品を控え、食物繊維の過剰摂取も避ける必要があります。
FODMAP食などの低発酵食品を中心とした食事が推奨されます。
2.正常な腸内環境の維持
適度な運動と規則正しい生活リズムで、腸管運動を正常に保つことが大切です。
また、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスの摂取も有効とされています。
プロバイオティクスとは、生きた微生物で、摂取することで宿主の健康に有益な影響を与えるものです。
乳酸菌、ビフィズス菌、酵母菌など、さまざまな種類の微生物が含まれます。
これらの微生物は、ヨーグルト、発酵食品、サプリメントなど、さまざまな食品や飲料に含まれています。
3.基礎疾患の予防と管理
糖尿病や自己免疫疾患などの基礎疾患をコントロールすることが重要です。
特に糖尿病では自律神経障害を予防する必要があります。
糖尿病における自律神経障害は糖尿病の合併症の1つで、高血糖状態が持続することで、内臓の働きを調節している自律神経が障害される病気です。
症状は、立ちくらみ、排尿障害、下痢、便秘などが現れます。
血糖値を良好にコントロールすることが、自律神経障害の予防と改善に重要です。
食事療法、運動療法、薬物療法など、総合的な治療が必要です。
4.必要以上の抗生物質使用の回避
抗生物質は腸内細菌叢を撹乱する可能性があるため、不必要な使用は避けましょう。
5.解剖学的異常のスクリーニング
先天的な腸管の形成異常などをスクリーニングし、必要に応じて手術を検討します。
6.ストレス対策
慢性的なストレスは自律神経の調節に影響を及ぼし、SIBO発症の一因になる可能性があります。
※SIBOには再発リスクが高いため、発症原因に応じた対策と生活習慣の改善が予防に重要となります。
基礎疾患のコントロールと、腸内環境を整える食生活が大切なポイントとなります。