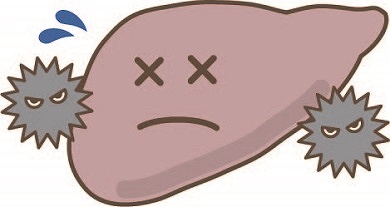C型肝炎の初期症状については、多くの場合は無症状であることが特徴的です。
感染しても自覚症状がほとんどなく、放置されがちです。
しかし、一部の人では以下のような初期症状が現れる可能性があります。
・全身倦怠感
・食欲不振
・上腹部の鈍痛や不快感
・吐き気
・黄疸(皮膚や目の白い部分が黄色くなる)
これらの症状は非常にあいまいなため、C型肝炎に特異的な症状とはいえません。
※多くの場合、感染後数週間から数カ月経ってから徐々に症状が現れる傾向にあります。
初期症状が現れずに慢性化すると、多くは無症状のまま経過しますが、肝硬変や肝がんなどの重篤な合併症を引き起こすリスクが高くなります。
そのため、がん検診など定期的な検査で早期発見に努めることが重要です。
高リスクグループ(輸血歴のある人、針刺し事故歴のある医療従事者など)は特に注意が必要です。
初期症状があれば、早期に医療機関を受診し、専門的検査で確定診断を受けることをおすすめします。
C型肝炎ウイルスの早期発見と適切な治療が、肝硬変や肝がんの発症を予防する上で重要となります。
C型肝炎 原因 合併症
C型肝炎の原因と合併症について詳しく説明します。
【原因】
C型肝炎はC型肝炎ウイルス(HCV)による感染が原因です。
このウイルスは以下の経路で感染が起こります。
・輸血による感染(現在はドナースクリーニングが行われているため稀)
・患者と医療従事者の間での針刺し事故による血液曝露
・薬物使用者が注射器などを共有することによる感染
・産科的な感染(母子感染)
・性的暴行による感染(稀)
HCVは血液を介して体内に入り、主に肝臓の細胞を攻撃します。
ウイルスに対する免疫反応が十分でないと、ウイルスを排除できずに慢性化します。
【合併症】
C型慢性肝炎が長期にわたり放置されると、以下の重篤な合併症が引き起こされる可能性があります。
・肝硬変:肝臓が線維化して硬くなり、機能が低下
・肝がん:特に肝硬変が進行すると発症リスクが高まる
・肝性脳症:肝硬変が進むと意識障害などが起こる
・食道静脈瘤:門脈圧が高まり食道の静脈が剥離する
・肝不全:肝臓の機能が著しく低下し、生命が危険に曝される
これらの合併症は早期発見と適切な治療が重要です。
特に最近では革新的な経口抗ウイルス薬が開発され、C型肝炎の治癒が期待できるようになりました。
C型肝炎 治療 完治
C型肝炎の治療と完治について詳しく説明します。
【治療】
C型肝炎の治療は、主に経口のダイレクトアクティングアンチヴァイラル薬(DAA)が用いられます。
DAA治療は従来のインターフェロン治療に比べ、副作用が軽く、短期間で高い治癒率が期待できます。
代表的なDAAには以下のようなものがあります。
・NS5Aタンパク質阻害剤:ダクラタスビル、レディパスビル、エルバスビル
・NS3/4Aプロテアーゼ阻害剤:グラゾプレビル、アスナプレビル
・ヌクレオチド系NS5Bポリメラーゼ阻害剤:ソホスブビル
これらを2~3剤併用して8~12週間の内服治療を行います。
ウイルス性状や遺伝子型、合併症の有無などに応じて、最適な薬剤を選択します。
C型肝炎ウイルスには、遺伝子の塩基配列の違いにより1~7までの主要な遺伝子型が存在します。
治療の選択や効果予測において、ウイルスの遺伝子型を把握することが重要視されています。
遺伝子型別の内訳は以下の通りです。
・遺伝子型1型(1a、1b): 世界中で最も一般的
・遺伝子型2型(2a、2b):欧州や日本で比較的多い
・遺伝子型3型:南アジアで最も多い
・遺伝子型4型: 中東やアフリカに多い
・遺伝子型5型、6型: 南アフリカ、香港などで散発的に見られる
※特に日本国内では、遺伝子型1型(1b)が約70%と最も多く、次いで2型(2a、2b)が約30%を占めています。
治療薬の選択や効果予測において、ウイルスの遺伝子型を正しく把握することが不可欠とされています。
【完治の判定】
治療終了後12週間経過し、血液検査でHCVが陰性化した状態が持続している場合、C型肝炎ウイルスが完全に排除できたと判断されます。
これをSVR(Sustained Virologic Response)と呼び、完治と判定されます。
SVR達成率は、最新のDAAでは95%以上と極めて高い水準にあります。
インターフェロン治療時代の60~80%から大幅に向上しました。
※ただし、完治後も一定の割合で肝発癌のリスクが残存するため、肝硬変患者などはその後も定期的な画像検査が必要とされています。
C型肝炎 薬の副作用 致死率
C型肝炎の治療薬には様々な種類がありますが、一般的な副作用と致死率について説明します。
C型肝炎の標準治療薬は直接作用型抗ウイルス薬(DAA)です。
DAA製剤には以下のような副作用がみられる可能性があります。
・疲労感
・頭痛
・吐き気
・下痢
・不眠
・皮疹
・関節痛
・うつ症状
しかし、これらの副作用は概して軽度で、治療中止を必要とする頻度は低いとされています。
DAA製剤の致死率は極めて低く、0.1%以下と報告されています。
一方、DAA導入以前に使用されていたインターフェロン製剤は、より重篤な副作用が問題となっていました。
・重度の疲労感
・発熱
・食欲不振
・精神症状(うつ、不安)
・血液障害
・甲状腺機能障害
インターフェロン製剤の致死率は0.1~1%程度と推定されていました。
現在のDAA製剤による治療では、重篤な副作用や致死的な事象は極めてまれですが、個人差はあります。
自覚症状が気になる場合は、必ず主治医に相談することが重要です。
適切な対処により、副作用がコントロールできる可能性が高くなります。
C型肝炎ウイルス自体の致死率については、感染初期から経過を追って見る必要があります。
・急性C型肝炎の致死率は非常に低く、概ね0.1%未満とされています。
多くの場合は自然治癒し、慢性な状態に移行しません。
・一方、慢性C型肝炎に移行した場合、長期間放置すると以下のようなリスクが高まります。
① 肝硬変(慢性)への進行率: 20~30%
② 肝細胞がん(肝がん)発症率: 1~4%
・肝硬変に進行した患者の5年生存率は約80%程度です。
つまり、約20%の方が5年以内に亡くなる可能性があります。
・一方、肝がんを発症した場合の5年生存率は約30%前後と極めて予後不良です。
※つまり、C型肝炎ウイルスそのものの致死率は低いものの、放置すると肝硬変や肝がんを発症するリスクが高まり、その際の致死率が上がるという課題があるということになります。
適切な時期に抗ウイルス治療を受けることで、これらの重篤な合併症のリスクを大幅に下げられることから、早期発見と治療開始が重要とされています。