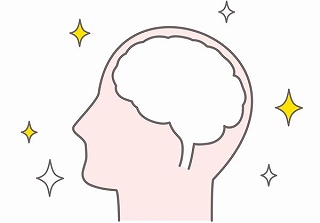将棋
将棋は、何千何万通りという駒の動きを読み切り、その中から最善の一手を選び抜いて戦う競技。
羽生善治九段によると、直感の7割は正しい。
理化学研究所で脳を研究をしている 田中啓治氏によると、
将棋のプロとアマチュアの高段者に来てもらって、詰将棋の問題を短時間で解いて貰った。
MRIに入って詰将棋の問題を見せる。1秒間見て次の一手を答えるというもの。
・羽生九段の正解率は80%
・他のプロ棋士達も70~80%
・アマチュアは40~50%
※大脳皮質(思考や推理を司る)には大差はなかった。
脳の深いところにある「大脳基底核」の活動が活発だった。
ある場面の中で1番いいものを短時間で選ぶ。
大脳基底核の選択こそがひらめきの本質。
大脳基底核はカンブリア紀には生物に備わっていたという説もある進化的に古い脳。
行為を自動化していく、自動的な行為というのは習慣。
大脳基底核は習慣の形成及び実行に関わると考えられている。
大脳基底核は習慣的な無意識の活動で働く。
プロ棋士はほとんど毎回正解を思いついてしまうのではないか。
田中寅彦九段によると、
盤面をみて目をつぶる、それで詰将棋の答えを頭の中で出すという訓練を子供の頃からやったという。
回数を重ねると詰む手が気持ちよくなる。
詰まない手は気持ちが悪い手。
アマチュアの方は算数をやっている感じ、プロは音楽か美術をやっているような感じ。
絵画を見ているような感じで次の手に行き着く。
大脳基底核は情動にも関わっている。
記憶が構造化されて新しいアイデアができていくのかもしれない。
アインシュタインの脳
人の脳は情報伝達の要である神経細胞が張り巡らされている。
その周りを埋めつくすように存在するグリア細胞。
アインシュタインは、そのグリア細胞を一般の人より1.7倍も多く持っていることが分かっている。
東北大学 松井広教授によると、
神経細胞から放出されるメッセージを伝えるグルタミン酸は、一部がグリア細胞でキャッチ、増幅させた上で次の神経細胞に送り出す。
グリア細胞から入力があると、同じトレーニングをしてもより早く簡単に学習が成立すると考えられている。
グリア細胞の機能としては、伝達物質、代謝産物、イオンなどを放出して脳内の環境を変える。
またグリア細胞は記憶にも関わっている。
人の脳からグリア細胞を取り出しマウスの脳に移植した。
その結果マウスの学習、課題の成績が上がった。
アインシュタインは、グリア細胞の多さによって、アイデアの結び付け方が違った可能性がある。
突拍子もないアイデアを結びつける力が強かったのかもしれない。
ひらめきを産む心の散歩
京都大学 苧坂直行教授によると、
一見何もしていない脳もかなりのエネルギーを消費している。
人間らしさを生み出すための遊びの脳の状態を、デフォルト・モードと呼ばれている。
そのモードの時には、内側前頭前野(心や精神を司る)、後部の帯状回、下部の頭長小葉の一部が盛んに働いている。
デフォルト・モード・ネットワークの面白い点は、マインドワンダリングという現象が起こる。
マインドワンダリング=心の散歩
心がふらふらと思いつくままに散歩する。
そのような状態の中で、ふとあるアイデア同士が偶然に組み合わさり新しい何かを見つける。
脳全体の使用エネルギーの60~80%をデフォルト・モードで消費している。
1日に2~3時間程度の心の散歩が推奨される。